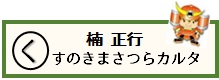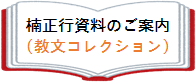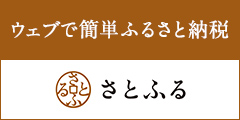����ҁE�q�ǂ������̏Ί炠�ӂ��X�@�l����s�����當���Z���^�[��
�l����s�����當���Z���^�[
���₢���킹��TEL.072-878-0020
��575-0021 ���{�l����s���5����2-16
�@���₢���킹��TEL.072-878-0020
��575-0021 ���{�l����s���5����2-16
�@�u��������揊�A�a�c���G��A�l����_�ЁA�n�Ӌ��`��̐Ք��v
���{�̍��ېԏ\���������\�ɂ����Ƃ�����n�Ӌ��̔��k
| ���� | ����27�N 7�� 9���i�ؗj���j |
| �s�� | ������揊�A�a�c���G��A�l����_�Ёi�ȏ�A�l����s�j�A �n�Ӌ��`��̐Ք�i���s�j |
��������揊
�@��^�䕗���O�����{���f���A�J�_������o���A�����͉J�V�~�ނ��Ɗo������ďW�܂����Q���҂��A�o���O�ɉJ�����܂�A�Ԓ��͑����̊����̒��Ŏs�������o�����܂����B
�@����́A�܂��s���U��Ƃ������Ƃ���A10��������ƖړI�n�́u������揊�v�ɓ������܂����B
�@���ꂢ�ɑ|�����߂�ꂽ�揊�Ɗ����12���[�g���ɂ��y�ԑ���̂����̂��i���{�w��V�R�L�O���j�����������}���Ă���܂����B
�@�u�t�̐�J�́A�u�͓������}��v�Ɍf�ڂ���Ă���2���̊G�u�l����荇��@�퐳�s�����v�Ɓu�퐳�s���@��ˁv�̊g��R�s�[����ɁA���l����̍��킪�s��ꂽ����3�N�i1348�j1��5�������̂��̒n�̗l�q��z�����Ă����������ƁA��o���܂����B
�@���͂��̂�����͏Z��Ɉ͂܂�Ă��܂����A������667�N�O�̂��̒n�́A2���̊G����z�����āA�����炭���ɔѐ��R�A���ɐ[��r�Ƃ��̎��ӂ̎�����ԂŁA�l�Ƃ��قƂ�ǂȂ��A���̂�����͎��n�ɐ����鈯�Ȃǂ̐A���������Ă������̂Ǝv���܂��B
�@���s�͂킸��1��R�ŁA���t��4���̑�R�Ƃ��̎l����̒n�ʼn�܂݂��A6���Ԃɂ��y�Ԍ����̖��A�O�ǓG�����A�퐳���ƂƂ��ɁA�u�G�̎�ɂ�����ȁv��23�̎Ⴓ�Ŗ��O�̎��𐋂����̂ł��B
�@���s�̈�̂́A������A�����ɓ����[��r�̒�h�ł��������ݒn�Ɉڂ���A�얳�����Ə��������肪���Ă��A�u��ˁv�ƌĂ�鋟�{�˂�����܂����B
�@���̌�A82�N�����āA2�{�̂����̂��̎���A�����A�N���o�Ĉꊔ�̂��Ƃ��a������́A���̏�����ݍ��݁A��ɐ������܂����B
�@
�@��n�̖k���Ɍ��Δ�́A������7���[�g��
 50�Z���`�̑�ŁA����8�N�A�哌�s�̗��Ԃ����o���A�^���A�����2�N��3�J���������A����11�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B�����܂����������Ă���̂́A��b���������肵�Ă��邩��ŁA5���[�g���l����4���[�g��50�Z���`�@�艺���A�n��ɏ��̐��O�C250�{��ł����݁A���̏�ɏ��̐���~���l�߁A�X�ɂ��̏����650�ƍ��I500�ʁA�ΊD200�U�������ł߂Ă��܂��B
50�Z���`�̑�ŁA����8�N�A�哌�s�̗��Ԃ����o���A�^���A�����2�N��3�J���������A����11�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B�����܂����������Ă���̂́A��b���������肵�Ă��邩��ŁA5���[�g���l����4���[�g��50�Z���`�@�艺���A�n��ɏ��̐��O�C250�{��ł����݁A���̏�ɏ��̐���~���l�߁A�X�ɂ��̏����650�ƍ��I500�ʁA�ΊD200�U�������ł߂Ă��܂��B�@�Δ�ɂ́A��v�ۗ��ʂ��u���]�O�ʓ퐳�s���b�V��v�ƍ���ł��܂��B
���a�c���G��
�@�퐳�s�̏]�Z��A�a�c���G�i���G�Ƃ������j�́A���s��������A������l���t���̖{�w�ɔ���A��|�����Ƃ��܂������A�G�Ɍ��j���a���Ă��܂��܂��B
�@���̎��A���܂�̉������ɁA���G�͓{��̎p�̂܂���H������A�ڂ����J���A�G���ɂ�݂��āA��Ɋ��ݕt�����܂��������悤�Ƃ��܂���ł����B�G�́A���G�̋��낵���炪������ł��āA7����ɂ͂Ƃ��Ƃ�����ł��܂����Ɠ`����Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���̋������ɂ��₩���āA������v�ɂȂ�A���ɂ�����A�u���_����v�Ƃ��āA���̒n�͒n��̐l�X�ɓĂ��M���Ă��܂����B
�@���݂̕��́A�V��2�N�i1831�j�A���̉i�c�F�V�����Ă����̂ŁA�ʔv�^�E����1���[�g��20�Z���`�A���ʂɁw�a�c���G��m��x�A�w�ʂɁw�ނ�����ւ́@���������Ԃ́@���炵�����x�ƍ��܂�Ă��܂��B�쒩�ɏ}�����a�c���G�̕�ɗ��Ă݂�A��ʂɃX�X�L��������A�H���������ʂ��Ă䂭����ŁA�l���̂͂��Ȃ��A���킳��Q�����̉�����������悤�ȋC������A�̈ӂƉ�����Ă��܂��B
�@���a43�N�A�l����J���g���[�N���u�i�S���t��j�̑����H�����ɁA�������Ւn����A�M�^��Όܗ֓��̘a�c���G�悪��������܂����B
�@���҂𑒂����ꏊ�͔�r�I�Z���Ԃ����J������āA���̌�ߊ�炸�A�J�����
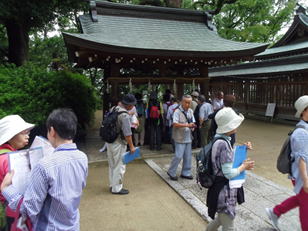 �邽�߂̕�n�𗣂ꂽ�ꏊ�ɐ݂��镗���u���搧�v�ƌĂсA�l����A�Ƃ�킯�c���̒n�ɂ��̗��搧�̌`�Ԃ��c���Ă��܂��B��ꎟ��n���w�I�o�J�x����n���w�}�C���o�J�x���ƌĂт܂�����������̕�͋��{�ˁA�}�C���o�J�Ǝv���܂��B
�邽�߂̕�n�𗣂ꂽ�ꏊ�ɐ݂��镗���u���搧�v�ƌĂсA�l����A�Ƃ�킯�c���̒n�ɂ��̗��搧�̌`�Ԃ��c���Ă��܂��B��ꎟ��n���w�I�o�J�x����n���w�}�C���o�J�x���ƌĂт܂�����������̕�͋��{�ˁA�}�C���o�J�Ǝv���܂��B���l����_��
�@�l����_�Ђł́A�����H�X�̏o�}�����A�����Q�q�������Ă��������܂����B
�@�����Q�q��A�����H�X����A�l����_�Бn���Ɋւ����j��G�s�\�[�h���ڂ����������Ă��������܂����B
�@����_�Ђɂ́A��ؐ����͂������̂��ƁA���s�A�v�q�̕����J���Ă������Ƃ���A�Z�g���c�_�Ђ̐_��A�O�q����𒆐S�ɔM�S�ɐ_�Бn�����肢�o�����̂́A�Ȃ��Ȃ�����������Ȃ������A�Ƃ̂��Ƃł��B�������A�n��̐l�X�̔M�S�Ȋ肢�������͂����A����22�N�ɂ��̒���������A����23�N4��5���Ɍ�����Ղ������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�܂��A�{�a�̐����ɂ́A�v�q�̕����J���E�_�Ђ��A�吳14�N10���ɒ�������܂����B
�@�_�Љ�قɈړ����āA�l����̍���̍u�b
�@���̌�A�����H�X�̌v�炢�Ő_�Љ�قɈړ����A�����H�X�����������k����J���A�����āA�u�t�̐�J����l����̍���A������6���ԁA���̍��i�ߑO10���j����\�̍��i�[��4���j�ɂ����āA����ǂ��āA�ڂ���������܂����B
�@�l����s�j�Ɍf�ڂ���Ă���l���덇��z��}�ɁA��J�����M�E���������l���덇��z��}�́A��1�������5���ɂ킽��Փˈʒu�A�����z�u�������ׂ��ɗ��Ƃ������̂ŁA�Q���҂͎���ǂ��ď����ꂽ�L�^�Ƃ��̑z��}�����Ȃ���A�M�S�ɕ�������܂����B�l���덇�팃����6���ԁiPDF�j�@�l���덇��z��}�iPDF�j
�@�l����̍���̈ʒu�ɂ��ẮA�l����s�j�����ƂɁA�哌�s�̏\�O���Ɏc��Č����̊��i���ؔł�A�Ð���`���鏬�����́u�Ð�c�v�u�n���L���v���\�O����сA�������n�̂����p�A���l����@���ǂ��猻�l����ی����Ɋ|������т��������ƂȂǂ������ɂ��Ă��܂��B
�@�u�b�̌�A�����Œ��H�����������܂����B
�@�T�v���C�Y�̍���
�@�o�X�c�A�[�Q���҂̂��ЂƂ�A�^�������̂��\���o�����������A�Ђ�
 ���ɁA������i�߂Ă������̂ŁA�ˑR�̃T�v���C�Y�A����Ɉꓯ���тł����B
���ɁA������i�߂Ă������̂ŁA�ˑR�̃T�v���C�Y�A����Ɉꓯ���тł����B�@���Ⴕ�Ă����������̂́A�^����i�ʐ^�E�j�ƁA��������i�ʐ^�����j�A��p����i�ʐ^���j�̎O�l�ŁA���̓��A�_�Љ�قɂ͓�ꑰ���v���]�C�������n��܂����B
�@��ڂ́A�ȉ��̎O��ł����B�Ȃ��A�����͒�������l�ɂ�����ł����B
�@�@ ������̕���@��F�������Y
�@�A ������̕���r���@��F�{�{�O��
�@�B �����@�@�@�@�@�@��F�͖�V��
���Ԓ��̍u�b
�@�l����_�Ђ���ɁA�}�C�N���o�X�ŁA�V�����Ɍ������r���A�Ԓ��ŁA��J����A�ʊi�����Ђɂ��Đ���������܂����B
�@�ʊi�����Ђ́A�S����28�Ђ���A����5�N�ɑn�����ꂽ����_�Ђ���1���ł��B
�@�쒩�W�ł́A��R�_�Ёi�����E�k���e�[�A�k�����Ɓj�A�����_�Ёi����E�V�c�`��j�A����_�Ёi�O�d�E����@�O�j�A�k���_�Ёi�O�d�E�k�����\�j�A���{��_�Ёi���E�k���e�[�A�k�����Ɓj�A�l����_�Ёi���E�퐳�s�j�A����_�Ёi���ɁE��ؐ����j�A���a�_�Ёi����E���a���N�j�A�e�r�_�Ёi�F�{�E�e�r�����j������܂��B
���n�Ӌ��A������`��̐Ք�
�@������`��̐Ք�́A�V�����w�i����E�n���S�j�̐����A��̉w�u�͂������v�̈�p�Ɍ����Ă��܂��B
�@���̔�́A���a15�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B
 �@�퐳�s�́A����2�N�i1347�j11��16���A�Z�g�E�V�����̐킢�ŁA�R�������A�א쌰���Ɛ킢�܂����A���̎R���R��������ƂȂ��đދp���A���̑ދp����R�������א�R���������ތ`�ŁA�����̓G�����ƌ�ނ��āA�n�Ӌ��ɎE�����܂��B
�@�퐳�s�́A����2�N�i1347�j11��16���A�Z�g�E�V�����̐킢�ŁA�R�������A�א쌰���Ɛ킢�܂����A���̎R���R��������ƂȂ��đދp���A���̑ދp����R�������א�R���������ތ`�ŁA�����̓G�����ƌ�ނ��āA�n�Ӌ��ɎE�����܂��B�@���̓n�Ӌ��ł́A�ދp���镺���������ꂸ�A�����̕������ɓ����o����܂����B
�@���̎��A���s�́w�G�����~���B�x
 �ƁA���V�ɓ��������鑽���̕��ɈߐH��^���A��������āA���A�������̂ł��B
�ƁA���V�ɓ��������鑽���̕��ɈߐH��^���A��������āA���A�������̂ł��B�@������A�n�Ӌ��̔��k�ł��B
�@���̍s�ׂ��̂ɁA���{�����ېԏ\���ɉ������邱�Ƃ��\�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�G�E�����Ȃ������������~�������ƂŗL���ȃi�C�`���Q�[���ɐ旧���ƁA500�N�O�̂��Ƃł���܂��B
�@���̓��̌��C�͂����ŏI���A�Q���҂́A��̉w�w�����Ɓx�̎U������܂����B
�@���̓���������s��������ό��D���ʂ�A�Q�Ԗ����}��ŗL���ȉ̐�L�d�̕`�����u�����ƒ��D�̐}�v�̍ڂ����p���t���b�g����ɁA��ʂ̕��i���y���݂܂����B
�@
�@����A9��10���́A�o�X�c�A�[�̍ŏI��ł��B
�@����̉w�Ձi���{���j�A��➉@�i���s�s�j�A���s���i�F���s�j��K��܂��B
�l����s�����當���Z���^�[�l����s�����當���Z���^�[
��575-0021
���{�l����s���5����2-16
TEL&FAX 072-878-0020
�w��Ǘ���
��ރG���^�[�v���C�Y�������
���ӌ��E���₢���킹
�v���C�o�V�[�|���V�[